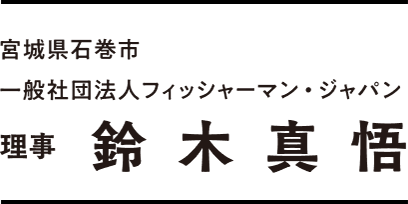フリーアナウンサーの堀井美香さんによる新連載がスタートです。ダイハツが作る軽自動車のように、地域に根ざしたひとの暮らしを豊かにしているキーパーソンを訪ねるこの企画。記念すべき第1回、おじゃましたのは宮城県女川町。一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン理事で株式会社マルキンの3代目、鈴木真悟さんのストーリーをお聞きします。

漁業の「新3K」を目指す。
鈴木真悟さんの挑戦。
仙台駅から、車を走らせ約1時間。雪のちらつく女川の地で、「キーパーソンじゃないんですが……」と謙遜しつつ鈴木真悟さんが取材班を迎えてくれた。子どもの頃は秋田の港町に住んでいたという堀井さんと、しばし「東北漁港トーク」で盛り上がる。
ここ10年で「漁業」のイメージが変化してきているとしたら、それは鈴木さんが仲間と立ち上げ、理事を務めるフィッシャーマン・ジャパンの功績にほかならない。それまでの「3K(汚い・危険・きつい)」のイメージから「新3K(カッコいい・稼げる・革新的)」への転換を目指し、挑戦を重ねてきた団体だ。この活動によってたくさんの若者が宮城にやってきて、漁業を生業にしているという。……十分、キーパーソンに見えるけれども。
鈴木さんの「本業」は、銀鮭の養殖を営む株式会社マルキンの3代目。これは約50年前、鈴木さんの祖父である欣一郎さんが始めた事業だ。
「鰹漁船のオーナーに大転身して大失敗したタイミングで、とある商社が鮭の試験養殖をやると耳にしたんです。で、『これは事業になる!』と」
はじめは海が汚れると反対の声もあったが、秋冬が旬だった鮭を春夏に出荷できたことで高値がつき、周りの漁師も次々と参入。女川の——宮城の鮭養殖の歴史がここに始まった。
とはいえ鈴木さんは跡を継ぐ気はなく、家族もそれを望んではいなかった。ただ、東京の大学に出たことで業界への見方は多少変わったという。
「実家が水産業って恥ずかしかったけど、みんな悪くない反応で。地元の魚を送ったらびっくりするくらい喜ばれて、松阪牛でお返しされたり。意外と魅力的なのかもな、とは思いました」
大学卒業後、全国展開の食の商社に入社すると気仙沼配属になり、担当は奇しくも水産中心。鈴木さんがそこで目の当たりにしたのは、価格競争オンリーの世界だった。どれだけ説明しても返ってくるのは「で、いくら?」という言葉。野菜のように、素材のよさやこだわりで勝負できないのか? そう悶々としていたときに起こったのが、東日本大震災だった。今しかない。鈴木さんは、実家に戻ることを決めた。

未来のため、若者に来てもらうには?
震災の被害と風評被害をはね返し自社事業が軌道に乗ってくると、鈴木さんの目はだんだんと地域に向き始める。若者がいない。下の世代が入ってくる未来も見えない。このままじゃ終わると感じていたとき、同じ課題意識を持つ、それぞれの浜(漁港)で活躍しているクセの強い若手漁師たちと出会う。そして2014年、彼らと「フィッシャーマン・ジャパン」を立ち上げた。地域のヒーロー誕生か!
……と思いきや、完全にはみ出し者扱いだったという。白い目で見られ、「余計なことをするな」と直接苦言を呈されることもあった。
「そういう外の声は、全然気になりませんでしたけどね。失敗して笑われても別にいいやってマインドです。それはずっと、今も変わらず」
団体として初期から掲げている大きな目標に、「水産業に携わる人を10年で1000人増やす」がある。その目標を達成するための施策を聞くと、やや意外な切り口だった。
「移住するとき、まずハードルになるのが住む場所なんです。そこで、シェアハウスを用意したらどうだろうと考えました。ライフスタイルごと提案してみようと。『社員寮』よりオシャレでしょう?」
そう笑う鈴木さんだが、多拠点で住まいを整備すれば、繁忙期の浜を移動しつつ漁をする「新しい漁師スタイル」が生まれるのではという目論見もあった。このアイデアが形になり、求人や生活全般をサポートする「トリトンプロジェクト」は走り出した。名は海の神にちなむ。


(左上)エサをスコップで投げ入れる。鮭専用のエサで、おいしい身を育てるために欠かせない。(右上)いけす1台あたりにつき3万匹の銀鮭が育てられている。エサをやるといきおいよく水面に現れる。(左下)脂ののった身は、焼いてもやわらかい。(右下)鮭の加工場。マルキンでは、養殖から加工まですべて自社で行っている
完全未経験から海の男になる
まさにトリトンプロジェクトを通じて大阪から石巻に移住し、漁業に携わるようになったのが29歳の後藤大樹さんだ。後藤さんの前職はまったくの異業種ではあるものの、一次産業にはずっと興味があったという。そしてコロナ禍で転職も視野に入れるようになり、フィッシャーマン・ジャパンのオンラインイベントに参加。住居費の負担が少ないことに背中を押されて(なんと研修中は無料!)えいやと転職し、4年前、石巻に移住した。
入社したのは、牡蠣養殖を営む「かねもと」。跡継ぎ不在でじきに畳むつもりだった親方だが、「やっぱり地元に漁業の仕事を残したい」とフィッシャーマン・ジャパンを通じて担い手を募集した。つまり、後藤さんは後継者候補。最近はSNSにも力を入れ、PRや加工品の販路に活用しようとしている。
「仕事はめちゃめちゃ楽しいです。親方も周りの人も応援してくれるし、あとは自分が頑張るだけ。よそ者を受け入れてくれたみなさんを裏切れないな、と背筋も伸びますが」
環境でいうと、労働時間は短くなくほぼ無休のハードな月はあるものの、残業代はしっかり出る。給与も毎年上がり、収入はついに前職時代を超えたのだとか! では、やりがいは?
「ベタなんですけど、おいしいって言われたときが一番うれしいですね」
漁業は「3K」であることは完全否定できないけれど、そこで頑張るからこそ「新3K」につながると思う、と後藤さんは語る。彼のようにそれぞれの矜持を胸にしたルーキーたちが、今、宮城には集っている。

(左上)牡蠣き場にて、後藤さんと「かねもと」の親方と奥さん。「お二人とも本当にいい人で、これからのことを一緒に考えてくれる。恵まれていますね」(後藤さん)(右上)牡蠣剥きは朝6時からスタート。出荷できる牡蠣かどうかを見極めながら、ていねいにスピーディに作業を進める。(左下)卓上流しそうめんのような機械で洗われる牡蠣。(右下)ぷりっとした牡蠣がボウルに溜まっていく。この牡蠣は、生食用としてスーパーなどに卸されるという。
次の10年も先頭ではみ出し続ける
「ある程度のことはやれた」手応えのある10年を経て、鈴木さんは今、予期しなかった問題に直面している。
「海洋環境の変化です。魚が獲れないし、どんどん小さくなっている」
魚が獲れなければ稼げない。魚を守らなければ次世代につながらない。危機感は強く、各メンバーが主体的に環境への取り組みを進めている。先の見えない問題である一方で、鈴木さんはこうした動きに期待をにじませる。
「みんな水産業のためにやるべきことは何か真剣に考えているし、やりたいこともある。そして彼らの活動に惹かれてまた若い人がやってくる。いい循環ができていますね」
若者がいない。——かつて鈴木さんが見た女川の風景はもうそこにはなく、若手漁師や志を共にする仲間たちが集っている。地域にとって若いエネルギーがどれだけ尊いかは語るまでもないだろう。「はみ出し者」が、地域に未来を連れてきたのだ。


堀井美香/1972年生まれ。95年から勤めたTBSアナウンサーを2022年3月に退社したのち、現在はフリーランスアナウンサーとして活動中。ジェーン・スーさんとの大人気ポッドキャスト『OVER THE SUN』を配信している。秋田県出身。
奥羽山脈を越えてきたカラカラの風が肌を刺し、女川は思ったより寒かった。
朝の冷え込みのままの牡蠣剥き場には、剥き手たちのキビキビと根気よく仕事をする姿。一つ一つ手作業で取り出される牡蠣は、乳白色に輝き、たっぷりとしたフォルムを見せつける。剥きたてをいただくと、これでもかと凝縮された旨みが体に沁みる。
雪が舞うなかマルキンの鈴木さんに船で沖合の生簀へと連れて行ってもらう。鈴木さんを待っていた何千もの鮭たちが、にわかに動き出し波を立てる。力強く投げ入れられる餌に体をしならせ飛び跳ねる。ロケ弁で人気がある塚田農場の銀鮭弁当はここの鮭を使っているというが、あの塩焼きが絶品である理由がわかる。
きっと、牡蠣も銀鮭も自覚している。誇りある仕事を、真剣にやり続ける人間たちに呼応して、自らも美しく美味しくあるべきだと。だから身は引き締まり、その味に無駄はない。そしてそれは女川の研ぎ澄まされた気候にも似ているのだ。